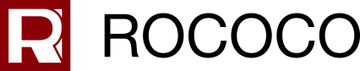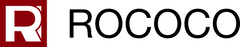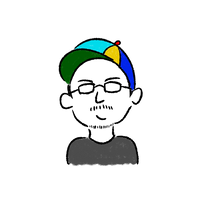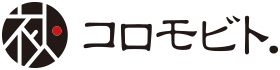大阪から奈良まで歩いてみた!靴下に込められた情熱、ROTOTOの工場潜入レポート
どうも! ウルトラウォーキングを愛し、ウォーキングの女神に愛されたい男、コロモビト.ライターのワタナベです。
前回は「靴下」について、名前の由来や歴史、豆知識などを紹介しました。
突然ですが、ROCOCOで人気のソックスブランドと言えば…SAY!
SO! ROTOTO! です。
実は先日、私(ワタナベ)、大阪から奈良まで歩いて、なんとROTOTOの工場に潜入してきました!
でも、安心してください。
「歩いて奈良まで行った道中」の模様はバッサリ省略し、今回はROTOTOのソックスがどのように作られているのか、その工場の様子に焦点を当ててお届けします。
さっそく、行ってみましょう!
ROTOTOの工場がある奈良県へ出発

【00:30】JR大阪駅前
大阪駅を出発! シューズはもちろん「On クラウドモンスター2」。約42kmの道のりを歩いて奈良へ向かいます。じゃ、行ってきます!

【09:30】近鉄大和高田駅前
はいっ!奈良県に到着。約9時間のウォーキングでしたが、あっという間に到着しました。
さっそく、ROTOTOのソックスが作られている工場へ向かいましょう。
ROTOTOの製品を作る工場に潜入
様々な最新の編機

写真:ずらりと並ぶ様々な編機その1
工場に到着。工場内には、靴下を作るための編機がずらり。驚くことに、日本では既に靴下を作る編機は製造されていないそうで、今使っている編機の多くは、50年以上前のものだとか。メンテナンスや改良を施しながら、今も現役で活躍している、まさに工場の大黒柱です。

写真:ずらりと並ぶ様々な編機その2
その一方、ヨーロッパやアジア圏から輸入された最新の編機も導入されています。
では、ROTOTOを代表するアイテム「R1001 DOUBLE FACE CREW SOCKS」を製造している編機に向かいましょう。
「R1001 DOUBLE FACE CREW SOCKS」の魅力

写真:ROTOTOと言えば「R1001」
まずは、「R1001 DOUBLE FACE CREW SOCKS」の特徴について簡単に説明をします。
このソックスは、表面にメリノウール、内側には未染色の太番手オーガニックコットンを使用し、スウェットシャツのような肉感を実現しています。内側のオーガニックコットンはループ状に編まれていて、ふっくらした肌触りが堪りません。
みなさんのクローゼットにある靴下と、「R1001」を一度見比べてみてください。多くの靴下は表と裏が同じ色ですが、「R1001」は表と裏で色が違います。実はこの秘密、編機にあるんです。
編機の秘密

写真:「R1001」を製造するための編機
「三層パイル編機」と呼ばれ、三種類の糸を使って靴下を編むことができる、かなり特殊な編機です。

写真:「R1001」を裏返すと現れるパイル地
「R1001」は、表側にウールの糸、裏側にコットンの糸、中間に伸縮性がある糸を使用して編まれているため、表と裏で色が異なる二種類の表情を持っており、商品名のダブルフェイスはここに由来しています。
ちなみに、一般的なパイルソックスは「二層パイル編機」を使い、表糸(表側と肌に当たるパイル)と裏糸(生地に伸縮性を加えるための糸)の2本糸で編まれています。
三層パイル編機の真実

写真:パイルが編まれていく様子
先ほど紹介した「三層パイル編機」、実は世界でこれを製造しているメーカーは存在しません。ROTOTOでは、既存の編機に工場独自で改造を施し、三種類の糸を使えるようにしています。

写真:複数取付けられている独自のパーツ
鉄板を削り出して穴を開け、溶接して部品も独自で開発するという驚きの手間がかかっています。しかも、同じ型番の編機であっても、製造時期によって微妙に仕様が異なるため、編機に合わせて改造方法も変えなければなりません。
「〇〇なソックスを作りたい」「〇〇を編める編機が必要だ」というアイデアを基に、編機の動作を計算して、必要なパーツも作り上げていく。それが完成するまでに、なんと3年かかることもあるのだとか。
編機メーカーが三層パイル編機を作らない理由

写真:編機を動かす心臓部
空飛ぶ車を作ろうとしている時代、三層パイル編機も現代の技術なら簡単に作れるのでは?って思っちゃいますよね。
結論から言うと、現代の技術があれば、三層パイル編み機は製造可能だと思います(工場長談)。
ではなぜ編機メーカーは製造をしないのか?それは三層パイル編機を使いこなすには、腕利きの技術者が必要になるからです。

写真:編まれる直前の三種類の糸
編む素材に合わせて編機の調整を行わなければならず、さらに毎月のメンテナンスも重要になってくる。編機をばらして掃除を行い再び組みなおして、再調整するのにベテランの技術者であっても1台につき6時間は要する。
多くの靴下メーカーは、そんな非効率な編機を無理して使うぐらいなら、一般的な編機で編める靴下を作る方が効率が良いし、編機メーカーも、手厚くサポートしなければならない三層パイル編機を、わざわざ製造する必要もありません。
ROTOTOのこだわり

写真:縫製くずからヒントを得て製作した靴下をまとめる輪っか
ROTOTOの靴下は、ただの靴下じゃない。どんなに手間がかかっても、この編機でしか作れない特別なソックスを生み出すために、時間を惜しまずにこだわり抜いている。そのこだわりと職人技が、ROTOTOのソックスを唯一無二にしているんですね。
次にROTOTOのソックスを見かけたら、ちょっとだけその裏に隠れた物語を思い浮かべてみてください。きっと「お!これ、いいな!」って思える瞬間が訪れるはずです。だって、こんなにも心を込めて作られてるんですからね。
おわりに

ROTOTOのソックスが「ただの靴下」じゃないってこと、工場で実際に見て、触れて、感じて、改めて実感しました。職人たちが手をかけて作り上げる一足一足には、まるで物語が詰まっているような気がします。その背景を知ると、靴下への愛着が一気に増して、毎日履くのが楽しみになりますね。

写真:私が愛用するソックス「HIKER TRASH」
さて、私がウルトラウォーキングで愛用しているソックスブランド「HIKER TRASH」。もちろん今回奈良まで歩く時も履いていました。実はこの「HIKER TRASH」のソックスもROTOTOが手掛けているんです。
次回は「HIKER TRASH」について熱く語ってみたいと思います。
「ハイカーのための最強ソックスブランド『ハイカートラッシュ』を語る」はこちら>>
「こんな記事が読んでみたい!」や「ワタナベ歩くの頑張れ!」のメッセージはこちらから。
コロモビト.ではあなたを魅力的にする情報をお届けしていきますので、またお越しいただけましたら幸いです。
よろしければブックマークよろしくお願いいたします。最後までお読みいただき、ありがとうございました!